
Event Report 2018.03.09
『かがやけジャパンブランド』セミナー(主催・日本経済新聞社、BrandLand JAPAN、The Wonder 500、後援・経済産業省、事業構想大学院大学、協力・チームニッポン社会振興財団)が、2017年12月の大阪セミナーを皮切りに、18年1月に名古屋、2月に福岡、3月に東京で開催されました。地方を元気にし、世界で通用するジャパンブランドとは何か。東京開催のセミナーの模様をリポートします。


経済産業省では海外の需要を効果的に取り込み、日本の魅力を経済成長につなげる「クールジャパン政策」を進めています。日本には地域地域でさまざまな魅力を持つ豊かな資源が豊富にあります。しかし、その高い技術力やサービスの素晴らしさだけに頼っていては、新たな展開は生まれません。経済産業省が実施している「JAPANブラント等プロデュース支援事業」は、地域が持つそうした資源をグローバルな視点を備えたプロデューサーや優れた専門性を有するデザイナーなど外部人材と組み合わせることで、その産品にストーリーを持たせ、海外市場や外国人観光客などのターゲットニーズに合わせた商品として世界に届けていくことを狙いとしています。
地域資源の海外市場に合わせた磨き上げや海外への発信を経済産業省は「ローカルクールジャパン」と呼んで積極的に推進していますので、これから世界を目指す皆さんにはぜひ参考にしていただきたい。素晴らしい地域資源は、外国人旅行者にとっても魅力的であり、それを磨き上げて観光消費の底上げにつなげることで地域活性化にも寄与します。
本日のセミナーが多くの地域、中小企業、小規模事業者の皆さんの産品、技術、サービスを磨くきっかけとなり、魅力的な地域資源の一つひとつが「かがやくジャパンブランド」になることで、日本経済のさらなる成長への牽引力となることを願っています。
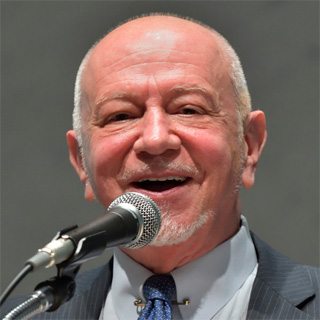
日本のデザインは、非常にシンプルでありながらエレガントで、私は大好きです。日本の建築や製品に対し、欧米人は強いあこがれを持っています。日本生まれの人が当たり前と思っていることでも、外国から来る人にとっては素晴らしく魅力的なものがたくさんあります。
ただし、その素晴らしさを伝える説明は不足していると思います。 例えば、日本酒の瓶。ラベルに英語で説明書きしているものはほとんどありません。高級なミネラルウォーターと勘違いして日本酒を購入した人を私は知っています。ボディーソープを買おうと思ってコンビニに行き、食器洗い用の洗剤を買ってしまった外国人もいます。ラベルに英語の解説を入れる、その小さな努力があるだけで、売り上げは増えると思います。
シャワートイレも同じです。輸出用には英語表記があり、シャワートイレ付きにすることで客室料金を高く設定しているヨーロッパの5つ星ホテルもあります。しかし、日本国内のトイレには日本語しか書いてありません。「止」の代わりに「STOP」と表記するのは難しいことではないと思います。
サンマリノには、東日本大震災で亡くなられた方々のための、小さなメモリアル神社があります。伊勢の職人さんにつくってもらった神社です。そこでは毎年6月に日本祭りが開催されますが、屋台で一番売れているのは抹茶アイスクリームで、2番目が日本酒です。どちらにも英語の説明があります。
サンマリノは小さな国ですが世界中から観光客が来て、この日本祭りで抹茶アイスと初めて出合う観光客もいます。日本国内でも、英語の説明を加えるひと手間を、ぜひ考えていただきたいと思います。

経済産業省ではふるさと名物応援事業として、世界にまだ知られていない日本が誇るべき地方商材500品を発掘して「Wonder 500」として認定してきました。予算措置は既に終了していますが、現在は民間事業者に継続して進めていただいています。
また、ふるさと名物応援事業に加え、クールジャパンによる地域活性化をローカルクールジャパンとして継続推進しています。2018年度事業では、JAPANブラント等プロデュース支援事業を通じて中小企業の海外進出プロジェクトを支援しています。事業者は海外のライフスタイルやニーズなどに詳しい外部のプロデューサーやデザイナーと組み、販路開拓を目指しています。本年度はBrandLand JAPANの対象として12件を採択しました。
この事業は販路改革だけでなくネットワーク構築も目的の一つとしており、プロジェクト同士の横つながりによる課題の共有と克服策の検討を柱に、グループディスカッションなども行っています。会議には国内外のシニアプロデューサーも参加し、現地でアドバイスをしています。
経済産業省では事業プロセスを国内外にPRし、情報提供を図ることで、同様の課題に直面している中小企業者の参考にしてもらいたいと考えています。将来的に海外展開を考えている事業者や、次世代プロデューサー候補の知識、経験の向上につながるように、公式ウエブサイト、フェイスブック、インスタグラムで情報公開をしていますのでせひ参照していただきたいと思います。

はじめに簡単なプレゼンテーションをお願いします。
2010年に経済産業省がクールジャパン室を設け、世界が共感する日本文化の再発見について発信し始めたころ、私は日本の小売業として何をすべきかについて考えたことがあります。日本のいいものがどこにあり、それをどうやって使い、どうやって自分のライフスタイルに織り込んでいくかということを、当の日本人は本当に分かっているのだろうか。そういうことも小売業として伝えていくことが大事なのではないかと考えました。
海外のメゾンは、日本のテキスタイルや素材、繊維などを日本人よりも先に見つけ、それを自分のブランドに使っているケースが数え切れないほどたくさんあります。シャネルは石巻の織物を相当使っていますし、ディオールは西陣織を使っています。
日本のものを使っているラグジュアリーブランドが世界のブランドと言われていて、なぜオールジャパンでこういうものがつくれないのか。ジャパンプレミアムをどんどんつくり、オールジャパンで海外に打って出ることが大事だと思います。
内閣府で政策参与を務める前、私は日本貿易振興機構(ジェトロ)で企業の海外展開と輸出のサポート業務を担当していました。現在はプロデューサーの支援や育成をテーマに、シニアプロデューサーという立場で関わっています。
初めて海外に出る場合、供給力のある商材ならば米国市場を優先すべきです。一番近いアジアに行く戦略もありますが、英語でビジネススキルを磨くと基本が身につき、ほかの国を開拓するときに非常に役立つからです。
ジェトロ時代の例として、米国の展示会に弁当箱を出品してもらったケースがあります。日本ではチェックや花柄だったのですが、米国人はシンプルモダンを好むため、パントンカラーのようにたくさんの色をそろえサンドイッチが入る大きさに変えたところ、1回の成約が5000万円以上という大型の商談につながりました。米国での成功のあとはヨーロッパに、次は中国へと販路を拡大できました。
海外展開でもインバウンドでも、いろいろなプラットホームに参加することが大事です。機能とデザインを掛け合わせたり、人材もネットワークをどんどん活用すべきです。
私は雑誌の宣伝会議の編集で地方創生マーケティングにかかわり、現在は事業構想大学院大学で地域の担い手を育成しています。事業構想大学院大学は2012年に文部科学大臣の認可を受け開学し、4月からは大阪と福岡にも開校します。
在学生は新規事業の担当者や起業を目指す人、自治体などで地方創生を担う人など多様です。社会を、会社を、地域を、自分自身をもっとよくしたい、成長させたいという当事者意識の強い23歳から60代まで幅広い人たちが集っています。
送り手が言いたいポイントと受け手が知りたいポイントには、ずれが生じがちです。ものづくりに一生懸命になればなるほど、送り手のストーリーが受け手に全然響かないということも起こります。
受け手にとってのストーリーをどうつくるか、それが一番重要です。外部アドバイザーの助言は、こうしたずれを正すのに大いに役立つはずです。受け手の客が深層心理でどんなことを考えているかを考え抜き、それを明文化する。受け手同士の情報共有が盛んな時代ですから、送り手もどんどん情報発信の場や機会を増やしていくべきです。

日本経済新聞社では、2016年11月に日経グループとして初めてクラウドファンディングサイトを立ち上げました。名前は「未来ショッピング」です。目的は、日経ID保有者800万人の力を借りて地方創生に貢献することと、イノベーションの流れをバックアップすることにあります。
普通のEマーケットは、ニーズがもともとあるコモディティー品を安く早く提供します。一方、未来ショッピングをはじめとするクラウドファンディングは、まだ世にないものに対して共感してもらい、潜在ニーズを捉えていこうというものです。これはまさに、地方創生にフィットした手法です。
資金集めだけではなく、予約販売サイトとして利用できる、テストマーケティングが行えるというメリットもあります。在庫を持つ必要はありません。テストをして売れそうであれば、在庫をつくればよいわけです。
ネット空間ですから、SNS(交流サイト)を通じて拡散もでき、応援者を集めることもできます。新聞社のサイトですから、メディアの露出も増えます。社会的信用やブランド構築にも役立ちますので、ぜひご活用いただければと思います。
大西さんは百貨店のトップとして現場を見てきて、プロジェクトマネジャーに向いている人はどのような人材だとお考えですか。
成功例を見ていると、プロジェクトマネジャーがとてもしっかりしています。しかし、彼らが有名かというと全くそうではない。キャリアや背景を聞いても、別にプロデューサーやプロジェクトマネジャーになろうと思ってなられた人でもない。共通しているのは、プロデューサーやプロジェクトマネジャーという役割以前に、人間として視野の広さや見識、感性を磨くことに熱心な人が多い。結局、人間力を磨いていたら、気がついたらプロジェクトマネジャーやプロデューサーになっていたという感じですね。
ジャパンブランドが海外でいけているかいけていないか、本音のところを浜野さんには伺いたい。

日本は国内市場向けの展開が中心だったため、経験力が足りていないと思います。そのため日本やアジア圏では知る人ぞ知るものでも、世界的にみればまだ浸透していないというのが日本のブランドの実態だと思います。楽観的に考えれば、それだけ将来性があるとも言えます。ただ、ヨーロッパのビッグブランドを見ていると、機能や感性に価値を見出して差別化しているだけではありません。今はものがあふれているので、自分の会社はこういう哲学でものをつくり出しているということを発信し、それに共鳴してもらうファンづくりを重視しています。グローバル市場で成功するためには、プラスアルファの工夫が必要になります。
田中さんには、これから地方創生を学んでいきたい、あるいは自分たちの手で事業を構想していきたいという人に対して、一言いただきたい。
クールジャパンで求められているプロデューサーの役割は、新しい価値を世の中に提供することだと思います。それは、新しい価値を世の中の人に気づかせる人ということです。地域のよさである伝統や歴史や風土、水や風まで全部分かった人でないと、いい仕事はできません。同時に、なぜやるのか、なんのためにやるのか、なぜそうしたいのかといったことを、外の人にも内の人にも徹底的によく話すことがポイントになると思います。未来を共有することで賛同者が増え、仲間や応援者ができます。ただ、対象者のことをよく知るということがまだ欠けていると思います。消費市場では、2割の人が8割の売り上げを支えていると言われています。そういうコアなファンをわくわくさせていくマーケティングの開発力も重要です。そうした心と技の両方に磨きをかければ、ジャパンブランドの未来は明るいと思います。
日本は先進国の中でも少子高齢化の先頭に立っています。逆に言うと、知見が他の国より進んでいるという優位性があります。地方創生マーケティングは少子高齢化の課題解決策の一つでもあります。皆さんと一緒に、これからどんどんチャレンジしていきたいと思います。本日はほんとうにありがとうございました。